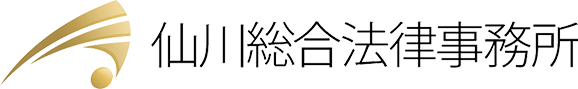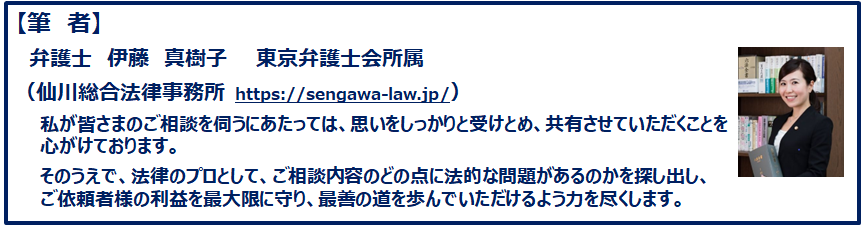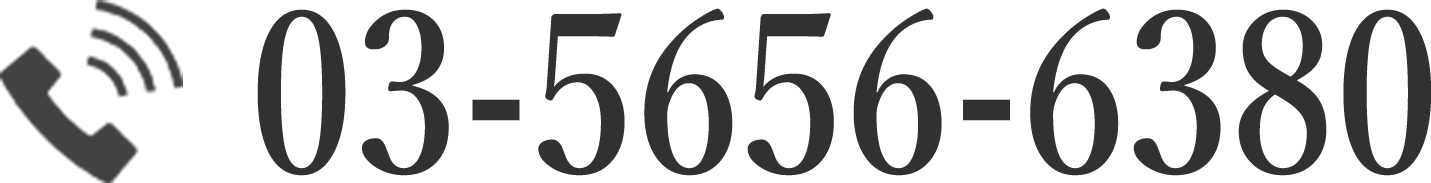手形の不渡りを回避する方法
その他
調布市の事業者で手形決済にお困りの方
不渡りとは
手形の不渡り(ふわたり)とは、手形や小切手を振り出した債務者に対し、支払人が支払呈示をしたにも関わらず、支払われないことを言います。
不渡事故を起こすと、手形交換所規則によって、交換所から全ての加盟金融機関に対して通知がなされますので、金融機関とのその後の取引に重大な支障を生じます。
さらに、6か月以内に2度目の不渡事故を起こすと、取引停止処分となってしまいます。
取引停止処分になると、全ての加盟金融機関との間で、当座勘定取引や貸出取引ができない状態となります。
その際、口座も凍結となることが一般です。
このように、手形の不渡事故により取引停止処分となると、その後の金融機関との取引が全面的に出来ない状態になってしまいます。
そのため、事業を継続することが事実上困難になり、倒産に至ることが多いのです。
 会社の破産と取締役の破産
会社の破産と取締役の破産
手形の不渡りを回避する方法
手形の期日が迫っているのに支払いが出来ない場合に、不渡りにせず事業を継続するための方法としては、民事再生の申立と同時に、弁済禁止の保全処分の申立を行うことが考えられます。
これにより、再生手続開始申立から開始決定までの間の債務者の財産を保全し、その結果、手形の決済ができなくても資金不足等による通常の不渡りとはならず、「0号不渡り」となり、不渡処分になりません。
ただし、そもそも再生手続が可能かどうかは、その後事業を再生していくことができる相応の蓋然性が前提となりますので、とにかく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
 債務整理を依頼する弁護士の選び方
債務整理を依頼する弁護士の選び方
新型コロナウイルスの影響を踏まえた取り扱い
今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、全国銀行協会は、新型コロナウイルス感染の影響を踏まえた手形・小切手等の扱いについて、不渡処分を当面猶予する特別措置を開始しています。
ただし、この措置はあくまで「不渡り」処分を猶予するものに過ぎず、支払義務自体を免除するものではありませんので、その後の資金繰りと事業の継続については慎重に判断していく必要があります。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上記措置については、本稿掲載時である令和2年5月時点のものであり、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。